|
|
|
|
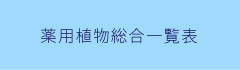
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| 薬草などの説明は、「医薬品医療機器等法」の範囲で対応しておりますが、不適切な表現などがある場合には、下記宛てにご連絡をお願い致します。 |
【注意事項】
各薬草ホームページの薬草コンテンツの説明・効能・用法などの説明は、薬理実験及び一般的な民間薬としての説明であり、「イー薬草・ドット・コム」などが保障するものでは、ありません。 |
【薬草参考文献】
水野瑞夫/家庭の民間薬・漢方薬、一般社団法人和ハーブ協会/和ハーブ図鑑、A・シエヴァリエ/世界薬用植物百科事典、牧野富太郎/日本植物図鑑、原色高山植物大図鑑、原色日本薬用植物図鑑、原色日本樹木図鑑、伊澤一男/薬用カラー大事典、橋本郁三/食べられる野生植物大事典、田中孝治/薬になる植物百科、水野瑞夫/食効、所鳳弘/薬草染、山渓/日本の野草・樹木・高山植物、山渓/樹に咲く花1・2・5・8、山渓/野草の名前春・夏・秋冬、木の大百科、木の名の由来、植物名の由来、園芸植物名の由来、草木染、続草木染
|
●当サイトはリンクフリーです。
●画像・文章等、当サイトの情報は著作権上無断で使用・引用できません。必ずお問い合わせください。
【監修】一般社団法人 和ハーブ協会 |
| |
|
ヨモギギク
(キク科ヨモギギク属:多年草:草丈 ~100センチ:花期 ~10月)
|
|
薬効
|
|
有毒 |
回虫駆除 |
疥癬虫・のみ・しらみ駆除/外用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 分布生育場所 |
|
科名:キク科/属名:ヨモギギク属
和名:蓬菊/英名:Tansy(タンジー)/学名:Tanacetum vulgare
ヨーロッパの温帯地方の荒地、道路わき、水辺など普通に見られる雑草のひとつ
日本では薬草として一部で栽培
北海道北部海岸地域、利尻島、礼文島に自生するエゾヨモギギクとは近縁種という
(←拡大画像はクリックします)
|
|
見分け方・特徴
|
茎は直立して高さ約1メートルになる多年草
葉は、2回羽状に深裂、各羽片の幅2~3ミリ、葉縁や羽片の間の葉柄にも鋸歯がある
花は7~10月頃に茎頂に枝別れした花柄を数個伸ばして、黄色の頭状花を平らな散房花序につける
頭花は、約1センチ、半球状、管状花だけで、キク科に多い回りの舌状花は無く、葉や頭花には特有の芳香がある
日本の北海道北部海岸地域、利尻島、礼文島に自生するエゾヨモギギクとの違いは、羽状の裂片がエゾヨモギギクは多いが、ヨモギギクは少ない
|
|
採集と調整
|
8月頃の開花期に頭花だけを採取して、風通しの良い場所で陰干しにして乾燥させる
|
|
薬効・用い方
|
成分は、樟脳(しょうのう)に類似する、ベータ・ツジョン、カンファー、ボルネオール、パラ・シメン、リモーネン、樟脳などの精油0.2%を含み、他に、フラボノイドのルテオリン、クエルセチン、イソムネチン、回虫駆除成分のフロログルシノールのタナセチン
腸内の回虫駆除に、1回量約10グラム、水0.3リットルを半量まで煎じて服用
揮発油は、月経を強く促進する、過少の月経の出血を刺激する
また、腸内の寄生虫の駆除や疥癬虫、のみやしらみの殺虫剤として用いていた
非常に毒性が強く現在はほとんど用いられていない、また、外用としてもほとんど用いられていない
また、妊娠中は用いてはいけない。特にヨモギギクの精油は法律で規制される場合もあるという
|
|
その他 |
名の由来は、不明だというが、キク科の菊(きく)とキク科の蓬(よもぎ)を掛け合わせた、ヨモギギクという名のセンスは面白い
ヨモギギクは、中世の本草家で12世紀のビンゲンの聖ヒルデガルドにより記述がある
それ以降、ヨモギギクは、駆虫用の薬草として用いられていた
イギリスでは、四旬節の間にヨモギギクのプリンを食べていて、16世紀のジョン・ジェラードはこのプリンを食べて「美味で胃によい」と記述しているという
|
左上 をクリックするとメインページへ戻ります。 をクリックするとメインページへ戻ります。
|
Photo Masayuki Tsuno
E-yakusou.com 2-6-2,sakaihigashi,nishi-ku,Niigata-shi,950-2041,Japan |
|